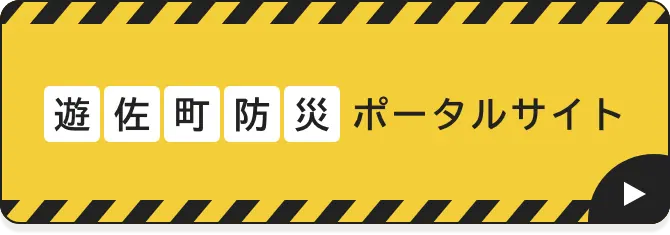噴火現象の説明
火山が噴火すると様々な現象が発生します。噴火活動の規模により、ここに示す以外にも「地殻変動」「地震」「地震に伴う地盤の液状化」「火山ガス」「空振(建物の窓ガラスが割れる事もあります)」などの災害が起きる可能性があります。
融雪による火山泥流
噴火によって雪が一気に融け、地面を削り取りながら、多量の 土砂や岩石を巻き込み、高速で 流れ下る現象です。谷を流れる 速度は時速数十キロメートルに達します。 平野部では谷から溢れ出て広い 範囲に氾濫し、橋や家を押し流したりします。1926年十勝岳で発生した火山泥流では144名の犠牲者がでました。
写真:1926年十勝岳で発生した火山泥流(No.10)
土石流
噴火によって斜面や谷の上流に火山灰が積もったとき、その後の雨によって土石流が発生しやすくなります。土石流が谷を流れ下る速度は時速10〜数十キロメートルに達します。巨礫や流木を含むため、平野部などの氾濫区域では家屋や田畑などに大きな被害が生じる危険な現象です。
写真:1997年八幡平で発生した土石流の跡(No.11)
噴火 降灰
噴火によって火口から噴石や火山灰が放出されます。噴石は主に火口から数キロメートル以内に落下します。時には直径1メートル以上の岩塊が飛ぶこともあります。火山灰は、上空の風に流され、風下側に降り積もります。 通常は西風が強いため山体の東側への影響が大きくなりますが、季節や天候によっては風向きが大きく変わることもあるので注意が必要になります。

写真:2000年有珠山噴火の被害(No.12)

写真:1991年雲仙普賢岳の降灰(No.13)
溶岩流
マグマが火口からあふれ出て流れたものが溶岩流です。 一般に流下速度が遅く徒歩で逃げることもできますが高温のため溶岩流の通過する場所は全てのものが焼きつくされ埋積されてしまいます。
写真:1986年伊豆大島の溶岩流(No.14)
火砕流(ハザードマップには範囲を示していません)
火口から出た高温の火山灰・溶岩片・火山ガスなどが混じり合い一気に斜面を流れて下る現象です。高温・高速(時速100キロメートル以上)で破壊力が大きく、とても危険な現象です。火砕流が通過したところは家屋は焼かれ土砂に埋もれます。1991年の雲仙普賢岳の噴火では火砕流で43名の方が犠牲になりました。

写真:1991年雲仙普賢岳の火砕流(No.15)

写真:1991年雲仙普賢岳火砕流の通過した跡(No.16)
山体崩壊・岩屑なだれ(ハザードマップには範囲を示していません)
噴火や地震が引き金となり山体の一部が一気に崩壊する現象です。崩壊した土砂や岩石は岩なだれとなり、時速100キロメートル以上で流れ下ります。発生頻度はそれほどおおくなりません。
写真:1888年磐梯山の山体崩壊地形(No.17)