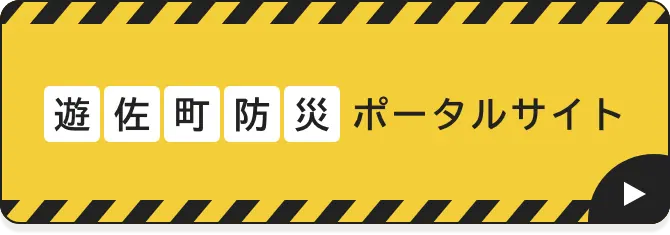保育園・認定こども園・小規模保育事業所について
町内施設の状況
保育園(保育所)は、就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。
杉の子幼稚園は、平成27年4月より、幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持つ認定こども園に移行しています。
はぐの家は、小規模保育事業所(A型)として、令和2年4月1日から開園しています。
町立吹浦保育園は令和7年度末をもって閉園することが決定しています。
町立保育園(公立)
| 施設名 | 設置者 | 郵便番号 | 所在地 | 定員 |
|---|---|---|---|---|
| 遊佐保育園 | 遊佐町 | 999-8301 | 遊佐町遊佐字五所ノ馬場4-1 | 80人 |
| 藤崎保育園 | 遊佐町 | 999-8434 | 遊佐町増穂字西田96 | 70人 |
| 吹浦保育園 | 遊佐町 | 999-8521 | 遊佐町吹浦字苗代34 | 80人 |
認定こども園(私立)
施設名
認定こども園 杉の子幼稚園
設置者
学校法人 杉の子学園
郵便番号
999-8301
所在地
遊佐町遊佐字高砂83
定員
115人
小規模保育事業所(私立)
施設名
小規模保育事業所 はぐの家
設置者
特定非営利活動法人 はぐの家
郵便番号
999-8301
所在地
遊佐町遊佐字丸ノ内134
定員
19人
利用手続きについて
保育園等の利用にあたって、子どもの教育・保育の必要性に応じて町から支給認定を受ける必要があります。
| 認定の種類 | 要件 | 対象施設等 |
|---|---|---|
| 1号認定 | 満3歳以上の就学前の子ども(2号認定除く) |
|
| 2号認定 | 満3歳以上の保育を必要とする子ども |
|
| 3号認定 | 満3歳未満の保育を必要とする子ども |
|
※幼稚園について、子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園を利用する場合は認定を受ける必要はありません。
2号認定・3号認定に係る保育を必要とする事由
- 就労
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学
- 虐待やDVのおそれ
- 育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として町が認める場合
保育の必要量に応じた支給認定区分
2号認定または3号認定は、保育の必要量に応じて「保育標準時間」「保育短時間」に区分されます。
| 区分 | 利用できる時間 |
|---|---|
| 保育標準時間(フルタイム就労等を想定) | 1日最大11時間+必要に応じ延長保育 |
| 保育短時間(パートタイム就労等を想定) | 1日最大8時間+必要に応じ延長保育 |
※「保育短時間区分」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1ヶ月当たり64時間です。
支給認定申請・利用申込み
- 1号認定を受けて利用する施設(幼稚園・認定こども園(幼稚園部分))
利用を希望する施設の園児募集に応募し、入園の内定後に利用施設を通じて1号認定の申請をしていただきます。 - 2号認定・3号認定を受けて利用する施設(保育園・認定こども園(保育部分))
翌年度4月以降の利用に係る支給認定申請・利用希望申込みは毎年10月に一斉受付します。
詳細は受付期間の事前に町広報 ホームページ等で公開します。
年度途中から利用を希望される場合は、子育て支援係までご相談下さい。
提出書類
- 施設型給付費等支給認定申請書兼保育所等利用希望申込書
- 就労証明書等(保育を必要とする事由によって提出書類が異なります。詳しくは記入上の注意をご覧下さい。)
提出書類は、下記からダウンロードできるほか、子育て支援係にご用意しています。
利用者負担額(保育料)
利用者負担額(保育料)は、認定区分と保護者の市町村民税所得割課税状況等に応じて町が決定します。
令和7年4月から保育料が改定(減額)となりました
遊佐町では県と町の共同の取り組みにより、令和3年9月から階層区分「第3階層」と「第4階層」の保育料無償化を実施してきましたが、令和7年度からは、この取り組みを一層進め、「第5階層から第7階層」の保育料を減額しています。今後も安心して子どもを産み育てられる遊佐町を目指し、子育て支援を推進してまいります。
副食費の実費徴収について
国による幼児教育・保育の無償化により、3~5歳児までの保育料が無償化されますが、これまで保育料の一部としてご負担いただいていた副食費(給食のおかずやおやつ等)は施設が定めた額を支払うこととなります。0~2歳児についてはこれまでどおり保育料に含まれます。
- 町立保育園については国の示す目安と同額の月額4,500円としています。
- 民間施設については、各施設へお問い合わせください。
- 1号認定及び2号認定の年収360万円未満相当世帯の子どもと第3子以降の子どもについては、国の基準により副食費が免除されます。(多子カウントは1号認定と2号認定で異なります。)
- 町独自の基準に該当する場合には免除されることがあります。