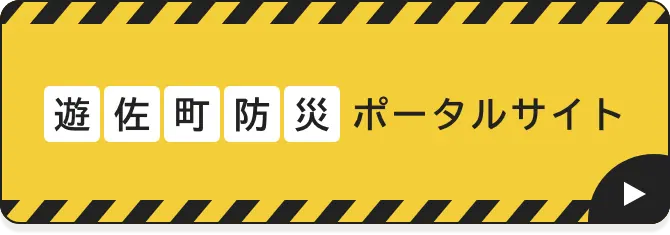吹浦田楽とは?
鳥海山大物忌神社吹浦口之宮には、古来相伝の舞楽が数多くあり、その起源・由来は定かではありませんが、少なくとも田楽の流行を極めた鎌倉時代まで遡るのではないかと言われています。
神仏習合時代には25坊一山衆徒が舞を行い、明治初年からは社家の手に委ねられてきましたが、社会情勢の変化により舞人も激減してきたことから昭和42年に吹浦田楽の保存伝承を目的に保存会を発足し、現在に至っています。
平成3年に国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財として選択され、平成5年に山形県の無形民俗文化財に指定されています。
上記写真をクリックすると、吹浦田楽の映像を閲覧できます。
奉納日
毎年5月4日・5日 鳥海山大物忌神社例大祭にて奉納
演目
- 花笠舞
- 大小の舞
- 諾冊二尊の舞
- お頭舞
- 猿田彦舞
- 巫女舞
- 御幣舞※
- 鉾舞※
- 剣舞※
- 翁舞※
- 稚児舞※
※現在舞われておりません。
吹浦田楽保存会 会員募集について
練習時期
毎年4月初めより例大祭に向けて土曜日か日曜日の18時頃から、会員の都合を聞きながら実施しております。
また、町外等からの公演依頼があった場合はそれに合わせた演目に絞って練習を行っています。
募集条件
舞人については体力的に男性のみで行っていますが、楽人(笛・太鼓等)については女性も募集しており、令和6年から女性の楽人(笛)も参加しています。
年齢及び住まいについての決まりはなく、練習、例大祭及び公演に参加できることが条件となります。
※会員の後継者不足、高齢化が深刻な問題となっています。ぜひ未来を担う若者たちからの積極的な応募をお待ちしています。