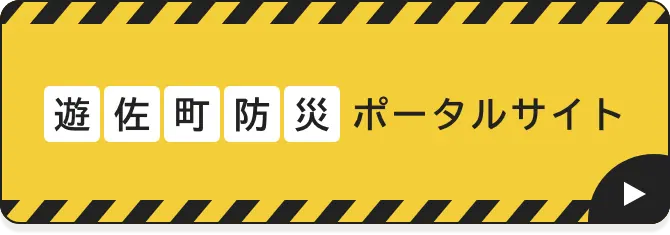ここでは埋蔵文化財と関連する手続きについて説明します。以下のリンクからページ内の項目へ飛ぶことができます。
事業者向け
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、地面に埋まっている文化財のことです。
昔の人々が生活をしてゆく中で残されたものであり、今でも人々の目に触れる形で残っている古墳や貝塚などはもちろん、土に埋もれた状態で残っている昔の家の跡や(遺構)、昔の人々が作った土器や石器など(遺物)が埋蔵文化財です。また、埋蔵文化財が埋まっている場所のことを「遺跡」と呼びます。
埋蔵文化財を保護する意味
文化財保護法では、埋蔵文化財の存在が知られている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。遊佐町には現在、210カ所の埋蔵文化財包蔵地があります。
埋蔵文化財は土の中に埋まっている文化財であるため、地面の上からではその範囲や状態を判断することが困難です。そもそも、地面に埋まっていることすら判明していない遺跡もあります。
このため、たくさんある埋蔵文化財の一部だけではなく、すべての埋蔵文化財が保護される対象となっています。
埋蔵文化財は我が国の歴史を知る上で大変貴重な資料で、一度壊してしまうと元に戻すことのできない国民共有の財産です。埋蔵文化財の保護について、ご理解とご協力をお願いいたします。
遺物を発見したら
土器や石器をなどの遺物は遺失物法が適用され、落とし物を拾った場合と同じような取扱いとなります。また、遺物は発見した場所や当時の状態の記録も重要な資料となるため、発見した状況を変えずに管内市町村の教育委員会へご連絡ください。
土木工事等の開発行為を行う前に
埋蔵文化財は地下に埋まった文化財であり、その性質上一度破壊されると復元することはできません。そのため、「周知の埋蔵文化財包蔵地」内で工事を実施する場合は、県または市町村の文化財担当課と協議する必要があります。
1.遺跡の有無の確認
町内で土木・建築工事を計画されている場合、事業予定地内に遺跡があるか確認する必要があります。確認方法は、「山形の宝マップ」(山形県管理サイト)(外部リンク)で確認するか、町教育課文化係へお問い合わせください。文化係への問い合わせは窓口へ直接お越しいただくか、電話、メール、FAXでも受け付けております。いずれの照会方法でも当該地の住所または地番をご用意ください。
事業予定地の中に遺跡がある、または隣接している
「2.届出の提出」をご覧ください。
事業予定地の中に遺跡がない
手続きは不要です。ただし、約1,000平方メートル以上の大規模な開発を計画している場合、遺跡の不時発見を防ぐため、事前調査にご協力いただいております。事前に文化係へお問い合わせください。
2.届出の提出
事業予定地が遺跡内にある、または隣接している場合、事業主は文化財保護法第93条による届出が必要となります。工事着手予定日の60日前までに、文化係までご提出ください。
届出様式
※詳しい記入方法や必要書類については文化係までお問い合わせください。
3.取扱いの決定
届出受付後、町で遺跡の現状を調査し、それを基に意見書を作成します。この意見書は届出と共に山形県へと提出し、工事が及ぼす遺跡への影響によって工事の取扱いが決定します。取扱いには、発掘調査、工事立会、慎重工事などがあります。
1.発掘調査
工事によって遺跡が破壊されるなど、地下の遺跡に影響を及ぼすと判断された場合、発掘調査を行って記録保存を行います。なお、発掘調査に係る費用は以下の取扱いとなります。
- 個人が営利目的ではなく行う住宅建設等:原則として公費で調査を実施します。
- 開発行為:開発事業者(原因者)負担を原則としております。ご理解とご協力をお願いいたします。
2.工事立会
遺跡に及ぼす影響がないと推定される深さの工事や、工事範囲が狭い場合、文化係職員が工事に立会い、状況に応じて対応します。
3.慎重工事
遺跡に大きな影響が及ばないと判断された場合はそのまま工事を進めてください。ただし、工事中に遺構や遺物が確認された場合は工事を中断し、文化係までご連絡ください。
工事中に遺跡を発見したら
工事の途中で埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第96条による届出が必要です。工事を中断し、速やかに文化係まで届け出てください。