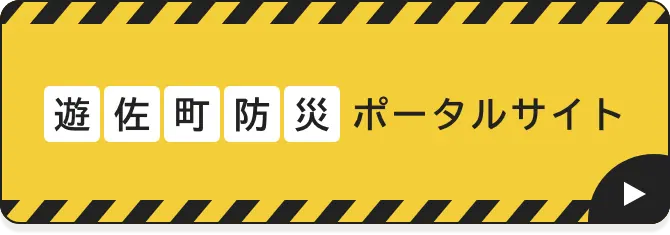少しの工夫でも効果的な省エネ方法をご紹介します
暑さが日に日に増してくる季節になりました。年々厳しくなる暑さに比例して、電力の使用量も増加傾向にあります。
最近では電気料だけではなくガス代も高騰し、何かと厳しい夏になりそうですが、「健康第一」を前提に、ほんの少しの工夫で出来る省エネ方法をご紹介します。ぜひ、ご家庭/職場で(可能な範囲内で)実践してみてください。
おうちで出来る省エネアクション
全家庭で消費電力の1%を節電すると毎日、コンビニ「約18,000店舗」(すごい!)が消費する電力と同程度のエネルギーが削減できます!
エアコン(節電効果約2~5%)
- ※室内でも熱中症になる場合があるので、「無理のない範囲で」行ってください。
- こまめにフィルター清掃をしましょう
- 設定温度を少しだけ上げましょう(室内が冷え過ぎない程度)
- 日中はカーテンやすだれなどで、窓からの日差しを避けましょう
照明(節電効果約2~3%)
- 室内の不要な照明は消しましょう
- 照明の明るさが調節出来る場合は、無理のない範囲内で明るさを下げましょう
テレビ・パソコン等(節電効果約1~2%)
- リモコンではなく本体の電源を切りましょう
- 長時間使わない場合は、コンセントからプラグを抜きましょう
- 画面の照度が調整できる場合は、照度を下げましょう(省エネモードにしましょう)
- 見ていない場合は消しましょう
冷蔵庫(節電効果約1%)
- 冷気を逃さないために、開け閉めする時間を減らしましょう
- 効率的に冷やすために庫内の整理をして、詰め込み過ぎないようにしましょう
- 「強から中」に温度調節をして、冷やし過ぎないようにしましょう
※食品の傷みにはご注意ください
温水洗浄便座(節電効果約0.3%)
- 使わない時はコンセントからプラグを抜きましょう
- 温水のオフ機能やタイマー機能を上手く利用しましょう
お風呂(ガス給湯器)
ガスの節約は水道の節約にもつながります。相乗効果を期待しましょう。
- シャワーを出しっぱなしにしないようにしましょう
- 節水型シャワーヘッドを使ってみましょう(簡単に取り付けられます)
- 給湯温度を低めに設定しましょう
自動車
ガソリンも高騰しています。出来るだけガソリンを消費しない方法は「エコドライブ」です。
- エコドライブを実践しましょう
- ふんわりアクセル
- 減速時は早めにアクセルから足を離す
- アイドリングストップ機能を使う、など
詳しくは「エコドライブ10のすすめ(PDF形式)」をご覧ください。
省エネ家電への買い替えもおススメです!
現在、山形県で8月31日(木)まで「やまがた省エネ家電買換えキャンペーン」を行っています。
エアコンや冷蔵庫などを買い換えるご予定のある方は、これを機にお得に買い換えてみませんか?
職場で出来る省エネアクション
全オフィスで消費電力の1%を節電すると毎日、「家庭約16万世帯」(遊佐町の世帯数の約32倍!)が消費する電力と同程度のエネルギーが削減できます!
エアコン(節電効果約2~4%)
- 執務室の冷やし過ぎに注意し、無理のない範囲内で設定温度を上げましょう
- 日中の日射を避けるために、ブラインドやカーテン、遮熱フィルムやすだれなどを活用しましょう
- 冷凍機の冷水出口温度を高めに設定し、ターボ冷凍機、ヒートポンプ等の動力を削減しましょう(※セントラル式空調の場合)
- 使用していないエリア(会議室・廊下など)があれば、空調を停止しましょう
照明(節電効果約3~13%)
- コントロール可能な範囲で執務室や店舗エリアの照明を間引きしましょう
- 使用していないエリアは消灯しましょう
OA機器(パソコン・コピー機など)
長時間席を離れる時は電源を切るか、スタンバイモードにしましょう
その他
- 温水洗浄便座は、使用状況を確認したうえで便座や水の温度設定を「OFF」にしたり、コンセントからプラグを抜いたりしましょう
- 電気ポットは、温度設定を見直す・省エネモードにするなど設定を確認しましょう
また、使わない時は電源を切りましょう
関連リンク・資料
リンク
- 省エネに関する情報については「省エネポータルサイト(資源エネルギー庁)(外部リンク)」からご確認ください。
- カーボンニュートラルや行動変容(ライフスタイルの切り替え)などに関する情報は脱炭素につながる「新しい豊かな暮らしを創る国民運動(環境省)(外部リンク)」からご確認ください。
パンフレット・リーフレット
- 「省エネリーフレット(家庭用)」(PDF形式)
上記のリンクでご紹介した方法をまとめたもの(家庭用) - 「夏季の省エネ・節電メニュー(家庭用)」(PDF形式)
リーフレットよりも詳細な方法を示したものはこちらからご確認ください。 - 「省エネリーフレット(事業者用)」(PDF形式)
上記のリンクでご紹介した方法をまとめたもの(職場用) - 「夏季の省エネ・節電メニュー(事業者用)」(PDF形式)
リーフレットよりも詳細な方法を示したものはこちらからご確認ください。