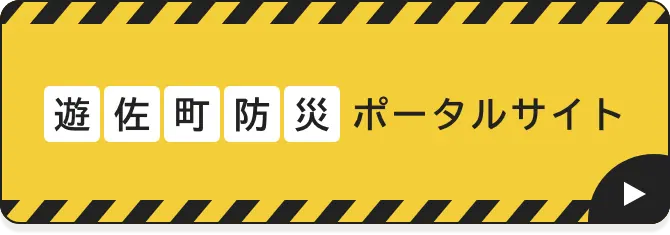罹災証明書・被災届出証明書について
「罹災証明書」は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2の規定に基づき、自然災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、地震、津波などの異常な自然現象により生ずる災害)により住家に被害が発生した場合に、被災の事実やその被害の程度などを証明するものです。「被災届出証明書」は、自然災害によって住家以外が被災した事実を町に届け出たことを証明するものです。
注意点
- 税金や保険料等の減免、補修に要する資金の貸付や公的な支援を受けたりするときに「罹災証明書」が必要となる場合があります。
- 交付申請期限を過ぎた場合、本来罹災証明書の交付対象となる住家であっても、時間の経過により被害の程度を正しく判定すること困難となることから罹災証明書ではなく被災届出証明書を交付します。
- 罹災証明書と被災届出証明書は全く別の書類であり、被災届出証明書では公的なの支援制度の対象となる世帯を証明するものにはなりません。
- 災害の程度等によっては、罹災証明書の交付を受けたとしても公的な支援が受けられない場合があります。
火災の罹災証明について
火災による被害の場合、酒田地区広域行政組合消防本部にて火災の罹災証明書を発行しています。詳しくは、直接消防本部予防課(0234-31-7147)へお問い合わせください。
落雷の罹災証明について
自然災害による被害が発生した場合、災害対策基本法第90条の2に基づき、町が調査を行い罹災証明書の発行を行っておりますが、落雷の場合、他の自然災害と違い、損害等の状況から判断することが難しく、被災原因が落雷によるものかどうかについて町で確認することができません。さらに、落雷の発生日時や発生場所を特定し、その事実を把握することは困難であるため、落雷による「罹災証明書」の発行を行いません。証明が必要な場合は「被災届出証明書」の申請を行ってください。
また、落雷により家屋が火災になった場合は、通常の火災と同様、火災の罹災証明書を酒田地区広域行政組合消防本部で発行しています。
被災状況の写真撮影・保存のお願い
罹災証明書の交付には、職員による住家の被害認定調査(現地調査(外観のみ))が必要となります。しかし、調査の前に建物の除却や被害箇所の特定ができなくなるような修理、片付け等を行ってしまうと調査が困難となります。そのため、あらかじめ被災状況を写真に撮影し保存していただきますようお願いします。
参考資料
受付窓口
1 受付時間
平日8時30分から17時15分まで
2 受付場所
総務課危機管理係
3 受付期限
発災日から3か月以内
証明書の種類(罹災証明書と被災届出証明書)
罹災証明書
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使用している建物)の被害について、町が現地調査を行い、被害の程度を証明するものです。
1 罹災証明書の対象
住家(災害発生時において、現実に居住のために使用している建物)
2 罹災証明書の証明事項
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)の6区分の被害の程度に分類されます。
被災届出証明書
「被災届出証明書」とは、自然災害による罹災証明書の対象とならない建物、建築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害を受けたという届出があったことを証明するものです。被害の状況が確認できる写真の添付が必要です。(現地調査は行わず、写真判定のみ)
1 被災届出証明書の対象
- 被害の程度の判定を必要としない場合
- 事業所、店舗、倉庫、車庫など、住家以外の建物
- カーポート、フェンス、車両、家財など
2 被災届出証明書の証明事項
自然災害によって被害を受けたことを、遊佐町に届け出たという事実(被害の程度や損害額は証明されません)
申請方法等
罹災証明書
1 申請に必要なもの
- 罹災証明書交付申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 被害の状況が確認できる写真等(自己判定方式の場合)
- 判定が必要な家屋の位置図・委任状(代理人が申請する場合)
2 被害が軽微な場合の「自己判定方式」について(例:床下浸水など)
住家の損傷割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、町職員等による現地調査を省略し、写真により被害認定を行います。写真は住家の全景(4方向から)と被害を受けた箇所について提出してください。
※印刷した写真を持参してください。また、自己判定方式について町職員から説明を受け、納得したうえで同意してください。
3 罹災証明書の被害程度に異議がある場合について
外観のみの1次調査で交付された罹災証明書の被害の程度に異議がある場合は、立ち入りの2次調査(再調査)の申請を行うことができます。
※上記の自己判定方式について同意された場合には、再調査は行いませんのでご注意ください
特記事項
- 2次調査を申請された時点で、1次調査で交付された罹災証明書の効力は失われます。
- 2次調査の結果、被害の程度が1次調査よりも下がる場合があります。その場合、1次調査の結果に戻ることはできません。2次調査の結果と1次調査と同じ場合は1次調査の罹災証明書を返却します。
- 2次調査を申請される場合は、1次調査で交付された罹災証明書の原本を提出してください。
- 2次調査の申請は、罹災証明書の交付を受けた日から1か月以内です。
※災害の発生、災害と被害の因果関係が確認できない場合や要件に該当しない場合は、罹災証明書を発行しない、または、申請と異なる種類の証明書(被災届出証明書)を発行する場合があります。
被災届出証明書
1 届出に必要なもの
- 被災届出書・本人確認書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 被害の状況が確認できる写真等(車両の場合は、ナンバープレートが確認できるもの)
- 判定が必要な家屋の位置図(現地調査のため)
- 委任状(代理人が申請する場合)
特記事項
- 現地調査を行わないため、写真で確認できない被害(動かない・電源が入らないなど)は、原則として証明できません。
- 被災届出証明書は、民事上の権利義務関係に効力を有するものではありません。
- なお、災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難となることから、被災した日から3か月を経過した場合は、罹災証明書の対象となる住家についても原則として被災届出証明書を交付します。
申請期限
証明書の申請期限は、災害発生日から時間が経過すると被害状況を適切に把握できなくなるため、原則として災害発生日から3か月です。
※災害の規模によっては延長される場合があります。
その他
- 災害の規模等によっては、調査・交付まで時間を要する場合があります。
- 罹災証明書及び被災届出証明書の交付枚数は、原則として災害ごとに1世帯1枚です。複数枚必要な場合は、ご自身でコピーしてください。
- 罹災証明書及び被災届出証明書の発行手数料は無料です。
- 災害の規模等によっては、罹災証明書の発行を受けたとしても、公的な支援が受けられない場合もあります。
- 原則として、登記されている建物、または、未登記でも固定資産税が課税されている建物が対象となります。