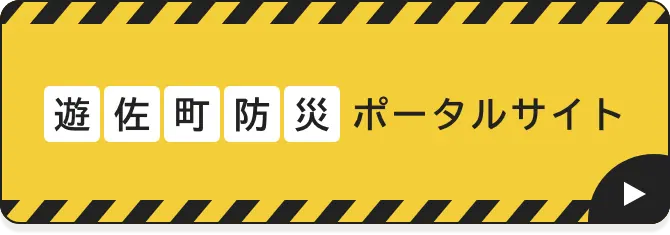税額について
「令和7年度 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料のお知らせ」をご覧ください。
納付の方法について
納付書・口座振替による支払い(普通徴収)と年金からの引き去りによる支払い(特別徴収)の2種類に分かれます。
普通徴収
7月から翌年2月までの8期に分けて納めます。遊佐町の指定金融機関の窓口で納めるか、口座振替をご利用ください。
※納付書で納付されている方は、令和5年度より地方税統一QRコードを利用したキャッシュレス決済での納付が可能となりました。
詳しくはこちらから確認ください。
※口座振替の手続きは、印鑑等をご持参のうえ、各金融機関窓口でお願いします。
特別徴収
下記の条件に当てはまる方は、手続きなしで特別徴収となります。
- 世帯主が国保被保険者であり、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満で構成される世帯
- 年金(老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金等)が年額18万円以上の方
※ただし、介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合は普通徴収となります。
特別徴収の金額は仮徴収と本徴収の2回に分けて算出されます。
- 仮徴収(4月、6月、8月)
同年2月分と同じ額の保険税を納めます。新たに特別徴収となる方は、前々年の所得などをもとに計算した金額を納めます。 - 本徴収(10月、12月、2月)
前年の所得などをもとに算出された保険税から、仮徴収を除いた額を3回に振り分けて納めます。
※国民健康保険税が特別徴収の方で、一定の要件に該当する方は、役場への申出により普通徴収(ただし、口座振替に限る)に切替することができます。